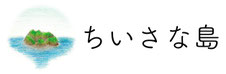写真に限らず映像もまた、その制作に携わるひとは大抵カメラの前に立つのを嫌う。それは撮影する側の人間として、ひとが写真や映像に映るとはどういうことかをよく知っているからである。ぼくもまたそうした一人である。ファインダー越しの映像は、時としてとても残酷だ。それは人間の脳のように選別するという能力が欠けているせいで、ありのままを映してしまうからだ。
あばたもえくぼであってほしいと思うのが人間で、あばたはあばたであるのが写真なり映像である。描写にえこひいきをしないという点においては、写真や映像はよく言えば平等主義なのかもしれない。
今まで人物を撮影するとなると相手は皆撮られるプロばかりだったし、一般人を撮影する場合でも大切なのは顔ではなくて発せられる言葉であった。だからレンズの先にいるひとの気持ちなど考えたこともなかった。
独立して一般の人たちを撮影することにしたとき、ひとはどのような気持ちでカメラの前に立つのかということを知っておいたほうがいいと思った。撮影とは非日常の世界である。とりわけポートレートのように簡易であれセットを組んで撮影する場合、非日常感は更に高まる。そうした状況で写真を撮らせてくれるひとの気持ちはやはり自分がカメラの前に立たなければわからないことである。そのひとの最高の表情を引き出すには、そのひとの気持ちに寄り添わなければできない。そしてそのためにはぼくは自分が経験してみる必要があった。
意を決してセットを組んだ。撮影はセルフタイマーで行う。シャッターボタンを押して、急いで椅子に座りポーズを作る。10秒があっという間だ。そしてカメラに戻って再生ボタンを押して愕然とする。このヘナチョコは誰だ?いや俺なんだが、俺ってこんなに不細工だったのか?
誰もいないのに一人で顔を赤くして冷や汗をかく。たぶんアングルが悪かったのだろう。もう一度やり直しだ。同じように10秒タイマーで撮影する。再生する。酷い。ひどすぎる。気が抜けたタコみたいな顔してる。そんなはずはない。俺はもうちょっとマシのはずだ。
目線を変え、座る向きを変え、姿勢を変え、顔の角度を変えてひたすら取り続けた。
最初は感情の中で恥ずかしさだけが突き抜けていたが段々と恥ずかしくなくなってくる。たぶん慣れてきたのだろう。それに伴い、自分の顔を冷静に見つめられるようになってきた。そしてわかったことは、自分の顔を過大評価していたということである。普段鏡で顔を見ているときも、自分の顔を脳内で200%増しに変換していたということである。
カメラの画面に映し出された自分の顔は、その圧倒的平等主義ゆえに現実であり事実しかない。受け入れろ、これがお前の顔なのだ。
自分の顔がようやくどういうものかとわかってくると、表情やアングルのコツがつかめてきた。人間だれしもマシに見える角度があるものだ。自撮りを繰り返すことで、そのマシな表情と角度をどうやって伝えたらいいのかがメソッドとして理解できたのは大きな収穫だ。経験と勘が悪いことはまったくないが、論理が立てばひとに教えることができる。
そしてそのマシを捉えることができれば、個人それぞれが持つ魅力を引き出すことは十分に可能であると自分の写真を眺めながら思う。結構マシに撮れていると思うけどどうだい?それとも単にナルシストなのかしら。
ライティングやフォトショップのテクニックは必要だが、それよりも写真を撮るという行為の上で必要なことがあると自撮りを繰り返して実感した。セルフポートレートは、たいへん不愉快な撮影だったが、同時に多くの洞察を得た。頭でわかっていることが真に理解しているとは限らない。こうして体を動かすことで血と肉に変えていくことが時として重要なのだろう。
セルフィーを撮っていて地味に面倒くさかったのがフォーカス合わせである。タイマー撮影の場合、コンティニュアスAFや瞳AFが効かないため(シャッターボタンを押したところでAFがロックされるため)、フォーカスが合わない写真を量産してしまった。当然ガイドを立てているが、座るときにそのガイドの位置と目の位置を完全に一致させることが困難だったのだ。座る位置を調整しつつポージングをして表情をつくる。これを10秒で行うのが大変だった。まあ通常の撮影では関係ないことであるが。
最後に写真をご覧いただいて終わりにしよう。