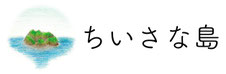子どもの頃干し柿が食べられなかった。どうにも風味が苦手だった。
なんだお前食べないのか、なら貰っちゃうよ。
そういって嬉しそうに父親が頬張っていたのを思い出す。
柿は好きだった。今でも一番好きなフルーツはと聞かれれば柿と即答するほど柿が好きである。
ところが干すと食べられなかった。
それがいつの頃からか気が付かないうちに干し柿が大好きになっていた。大人になったら好きに
なっていたのである。しかし同時に気がついたのは、干し柿はなかなか口に入らない食べ物であるということだった。
そう、干し柿は高級品だった。ピンキリあるとはいえ、キリの方だって結構なお値段がする。まことに高級なお菓子である。
その干し柿が久々に食べられるときたからこれは記念撮影をしなければなるまい。
乾燥した寒風にさらされて水分が蒸発して糖分が凝縮し、表面を粉が吹いたようになってもとの大きさの
半分以下になって形がへしゃげてようやく一人前の干し柿になる。苦労した分人間味が増すように、厳しい寒さを
乗り越えた干し柿ほどその佇まいは威厳に満ちてくる。しかしどうだろう、ひとたび噛みしめればじんわりと甘みが
滲み出して口中に広がり、得も言われぬ香気が鼻腔を抜けて脳髄を刺激する。
生の柿はどこか青臭いところがあるが、それが熟成したワインのように豊かな風合いとなってぼくの頬が緩む。
美味いなあ旨いなあなんと甘露なことかなあ。
幸いなことにあれほど干し柿に憧れた娘は一口たべていらないと言った。思い描いた幻想と違ったのだろう。
であるならば残った干し柿もぼくの口に届くのか?届かないのか?