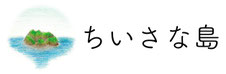“HUNTER”
ジョン・A・ハンターさんが書いたハンターという本を読んだ。まるで冗談みたいだが、ハンターさんはアフリカの猟師である。プロの狩猟家である。1952年に出版されたこの本は、ハンターさんの26年に渡る狩猟記である。日本語版が出版されたのは1957年の12月で、翌年の2月には26版も版を重ねているから当時のベストセラーだったのだろう。
アフリカの野生動物を狩る話だから読んでいて気持ちのいいものではない。なにしろハンターさんはのべ1000頭以上の象を殺し、1000頭以上のサイを殺し、1000頭以上のバッファローを殺し、1000頭以上のライオンを殺し、その他数え切れないほどのヒョウを殺し、ゼブラを殺し、インパラやその類を殺し、イボイノシシを殺し、とにかく撃ちまくって殺しまくっている。
なぜそんなに殺すのかと言えば、三つの理由がある。ひとつは当時野獣狩りは西洋の貴族、富豪を中心とした金持ちの余興であり娯楽だったからである。ハンターさんはそのガイド役として随行し獲物を仕留める手伝いをしていた。二つ目は商品としての狩猟である。象牙やサイの角、ライオンの毛皮を売って金を作るためである。最後は頭数コントロールと称した大量殺戮である。これは政府の依頼を受けて行う狩猟である。ヨーロッパの国々がアフリカを支配するようになると、もともと住んでいた現地人に狩りを禁止させ、農耕と家畜を奨励した。その結果、人口が増え農地拡大のために未開の地を分け入って野生動物と対立するのである。そしてハンターさんが派遣される。この手の仕事の場合、一度にサイを600頭とか象を数十頭とかぞっとするような数を射殺する。
だから狩猟の描写は最初の頃こそドキドキハラハラするが、次第に気分が悪くなって自分が殺したわけではないのにとんでもないことをしてしまったような気さえしてくる。現代に近づくと、狩猟客が減ってその代わりにカメラで撮影する客が主流に移ってくる。これで動物の殺害が減るのかと思いきや、写真目的の客でさえ結局迫力ある写真(つまりこちらに向かって猛襲してくる写真)が撮りたくなって、ハンターさんが撃ち殺すはめになる。そうしなかったらこちらがやられてしまうからである。まったく人間たちは食べるためでなく、ただ自分たちのJOYのために野生動物を殺すのであるから読んでいて暗くなる。
息子にこの狩猟の話をすると、そんなことをするやつは許せない。だから動物がいなくなってしまうんだ。なんでそんなひどいことをするんだ。と憤ったが、ぼくは言った。キミだって蟻を見つけたら見境なく踏みまくって殺しまくるだろ、なんでそんなことするの?
すると息子は蟻は数が多いからいいんだと言った。そうだよ、昔は野生動物もたくさんいたんだ。数が多いからみんな殺しても平気だったのさ。息子はまるで納得しない顔だった。
そんな殺戮の話だから読むのが嫌になるのかと言えば、その反対である。ぼくはページをめくる手をとめることができなくて電車を乗り過ごしたほどだった。なにがそんなに面白いのか。それは今から100年ほど昔のアフリカでくらす現地人の様子が克明に描かれているからである。外国人がアフリカでハンターになるには現地人の手助けが不可欠である。決してガイドやアシスタントなしに狩猟することはできない。だからハンターさんも数多くの部族とつきあいそれぞれの特徴を知っている。かれらは優秀な助手にもなるが、同時に根本的に我々と異なる考え方を持っているために様々なトラブルにも見舞われる。
例えば。夜のライオン狩りのことである。仕掛けた餌にライオンたちがやってきた。助手である現地人が懐中電灯でライオンを照らす。そこを別の場所に潜んだハンターさんが銃で仕留める。ライオンは懐中電灯の光にはあまり頓着しないらしい。ところが突然ライトが消えた。あたりは漆黒の闇と化す。ハンターさんは身の危険を感じた。ライオンは恐ろしいほどに闇に目がきく。こちらはなにも見えない。ハンターさんは死にものぐるいで叫びながら助手の潜む隠れ場所へと飛び込んだ。そこで助手はなにをしていたか。なんと懐中電灯をバラバラに分解していたのである。中身がどういうふうになっているかどうしても気になってしまったのだという。生命の危険があったハンターさんが激昂したのは言うまでもない。
アフリカの原住民たちが一番好む食べ物はなにか。それは肉である。それも生肉を食べる。ハンターさんが象を殺すと住民たちが群がって象に食らいつく。ハンターさんは象牙が取れればそれでいいので見ているとまたたく間に象は骨だけになってしまった。彼らはそれぞれ手に手製のナイフを持って死んだ象に向かっていく。あたりかまわずナイフをみんなが振るうから、そばにいるひとを切ってしまう。このままでは死人がでるとハンターさんは不安になって部族の長に相談して順番待ちをするようにお願いするのである。すごいのは切られたひとも怪我に気が付かないで象の肉に夢中になっているのだという。
食人の話も出てくる。食人習慣は多くの部族であったそうだ。生け捕りにした捕虜が奴隷として売れないと部分ごとに切って売るのだという。もっとも食人習慣は中国の水滸伝を読んでいてもわりと頻繁に登場するからタンパク質資源の乏しい地域では広く行われていたのだと思う。
あるとき随行のコックに今日の料理はなにかと聞くとスープだという。なかなか不思議な味がするが何の肉だかわからないで食べているとあんたは食べちゃいけない。タブーだとほかの黒人に注意される。聞けば通りがかりの黒人から人間の腕を買ったとのことである。ハンターさんは食欲をなくし部屋へと戻った。
ワカンバ族は勇敢で優秀な部族である。マサイ族はライオン狩りの名手であり、戦闘種族である。ピグミー族は森林に暮らすたいへん小柄な種族でとても賢いのだという。オカピを追ってピグミー族の暮らす森へやってきたとき、彼らのモラル意識の高さに驚く。世界一ではないかとハンターさんは言う。なぜならピグミー族には世界最古の職業が存在しなかったからである。彼らのエピソードはまるで飽きることがなく、次から次へと好奇心を刺激する。おそらくそれらのほとんどはもう失われてしまっているのだ。そして数多くの野生動物同様二度と戻ってくることはないだろう。
このHunterという本は、一狩猟家の記録であり、つまらぬ考察などが無い代わりに書き留めた事実がありありと眼前に浮かぶ。豊かな自然があり、豊かな人種に溢れ、生命に満ち満ちている。我々が今多様性などと口にしているが、それを言うのがはばかられるほど多様だった時代がかつてあったのである。ぼくを惹きつけてやまないのはまさにそこだった。